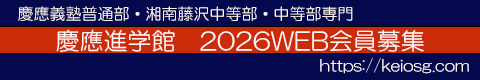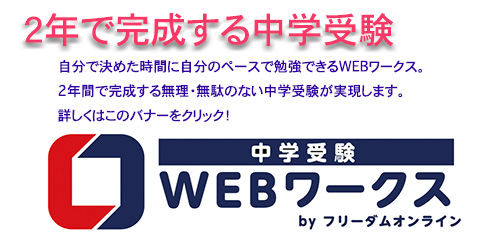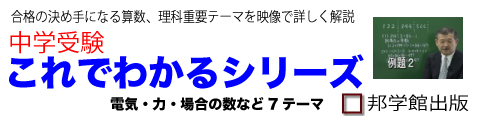どの塾でも、カリキュラムは決まっていて、そのカリキュラムに併せて昇降テストや組み分けテストがやってきます。
しかし、どの子も同じように進めるわけでは実はない。その週忙しいことはあるかもしれないし、またまだよくわかっていない、という場合もあるでしょう。しかし、そういうのは基本的に許されない、締め切りがあるわけだから、まあ、有無を言わせず試験は受けなければなりません。
試験を受けなければいけないのは仕方がないとしても、それでクラスが昇降するとやはり子どものモチベーションにも問題が出てくる。だから、クラス落ちを避けるためにテストを受けない、という子もたまにいるそうですが、しかし、そう何回もは許されない仕組みになっているそうです。
フリーダムは毎週カリキュラムが決まっていて、4回に1回月例テストがやってくるように出来ています。しかし、そのペースは勉強の進み具合によって違ってきます。
で、スタディールーム、スタディールームオンラインとも個別に進むから、先に進むこともできるし、後から受けることもできる。
5年生から海外でスタートした子は、半年遅れで月例テストを提出したこともありました。しかし、大事なことは、わかってからテストを受ける、ということで、別にフリーダムの場合は昇降がないから、それでも構わない。
納得してから、テストを受ければそれなりに点数も良くなるし、わかった、ということが納得できるので、それはそれでも良いわけです。
今の子どもたちの様子を見ていると、算数が好きで、算数だけばく進している子。逆に算数だけ、ゆっくり進んでいる子もいます。
またシステムで勉強するのが気に入って、先までどんどん進んでいる子もいます。
別に早く終わる必要はないが、無理して遅くする必要もない。簡単だと思うところは進み、大変だと思うところはゆっくりやれば良いのです。
例えば、終わらない課題については、空いている曜日を使って自分で勉強する。それでもわからなければ次の授業のときに聞けば良いので、その調整も学習管理者と相談すればいい。
子どもたちも自分の次の課題をどこで、どう実行するのかがわかるので、その週の過ごし方を決めやすい。
最終的に入試に間に合えば良いので、習い事や学校行事などとも併せて勉強を進めて欲しいと思います。