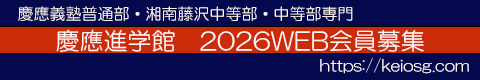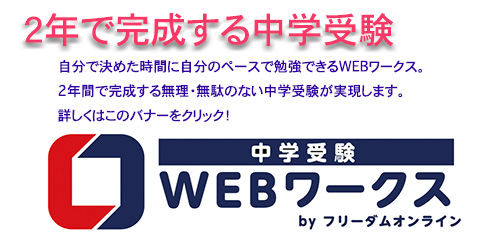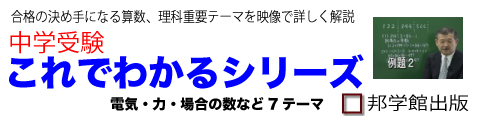小学生は、いろいろやりたいことが多いはずなのです。
サッカーの試合を見れば、サッカーをやりたくなるかもしれない。
スケートボードを見れば、自分もやってみたいと思うかもしれない。
そして、実際にそうやってがんばった子が代表になったり、オリンピックでメダルを取ったりしているわけで、だから、小さい時にそういう挑戦の機会を作ることが結構大事なのです。
しかし、今は塾が早くから始まっているので、どんどん挑戦する機会が減ってしまっている。
これはやはりちょっとかわいそうな感じがする。
受験勉強はまだまだ合理化する余地はたくさんあるので、小さい時はいろいろ挑戦してもらいたいと思います。
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事
併願校で良かった
今日の田中貴.com
モチベーションを探す機会